DMEF Direct / Interactive Marketing Research Summit
(2011年10月1・2日 米国マサチューセッツ州ボストン)
「Reference Group of Microblog Influence on the Consumer Decision Process: A Multiple Case Study on Tweets as Electronic Word-of-Mouth」
2011年DBA入学 太田 滋
2011年度DBAに入学した太田滋さんが、2011年10月1・2日開催のDMEF Direct / Interactive Marketing Research Summit(米国マサチューセッツ州ボストンで開催)で発表しました。発表タイトルは「Reference Group of Microblog Influence on the Consumer Decision Process: A Multiple Case Study on Tweets as Electronic Word-of-Mouth」です。太田さんに海外での学会発表の経験をご寄稿いただいた。
海外での学会発表:多くの困難があるが、世界のレベルを知り、学び、友人をつくることに比べればたいしたことはない
2011年DBA入学 太田 滋
今、私はボストンで原稿を書いている。学会発表を終えた2日後、熱も冷めやまない状態である。
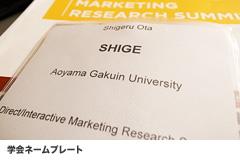
MBA時に書いたリサーチペーパーを、海外の学会で発表することは始めから決めていた。学会の申し込みをしたのが5月末。その2週間後にAcceptの通知を受けた。Proceedingに掲載するFinal abstractの原稿提出、プレゼン資料の準備、渡米の手配や各種事務手続きで時間は刻々と過ぎていった。
プレゼンの準備も終え、資料も完成したのが学会発表の2週間前だった。主査・副査の先生方にお時間を頂き、出発前に予行プレゼンの機会を頂いた。「何が一番言いたいのかわからない」、「資料に無駄が多い」、「インパクトが足りない」、「世界に何をアピールしたいんだ」・・・。60分間、あらゆる角度から酷評を頂いた。
もう一度やり直し。資料も作り直し。その日の夜、学会に参加する目的と初心を再度確認した。
- 世界の研究に少しでも貢献すること
- 自分の研究に対するフィードバックを得ること
- 日本の研究者として世界にアピールすること

学会の発表が目的ではない。発表を通じて、世界に貢献することに意味がある。再度、資料を練り直し、プレゼンも“発表”から“魅了”する内容に大幅修正した。ボストンに向かう飛行機の中でも、プレゼンのイメージトレーニングを行った。
そして、10月1日。発表当日である。学会の参加者は138名。当日朝に配布された参加者名簿をみると、発表者の9割がProfessorもしくはAssistant Professorだった。日本からの参加者は私だけ。同じアジア人がいたと思って、声をかけたら、Harvard Business Schoolの博士課程の学生だった。
発表は15分間。発表直前に頭が真っ白になった。準備を重ねたプレゼン台本は忘れた。しかし、冒頭の第一声を発してから、なぜか緊張はほぐれていった。プレゼン終了。拍手を浴びた。質疑応答セッションでは私に質問が集中した。研究の前提、研究成果の解釈、ちょっとした批判も頂いた。発表後も数名からお声掛け頂き、研究の詳細説明をした。参加者と議論をしながら、次の研究に活かそうと思った。

これが私にとって初めての学会発表の経験である。たった一回の発表から私が得たことをここで述べるのは甚だおこがましいと思う。しかし、これだけは言える。日本の研究者は海外に出るべきだ。時差ぼけもある。旅費もかかる。慣れない英語は緊張する。研究も二カ国語でやると余計時間もかかるし、プレゼンも海外向けに変える必要がある。それでも、世界のレベルを知り、学び、友人をつくることに比べれば大したことはない。
今回の発表で一定の成果を得ることができたのは、発表2週間前の予行プレゼンがあったからだと強く感じている。あの予行プレゼンでご指導頂いたことを、発表直前に思い出したことで、自信をもってプレゼンできたのだと思う。主査の岩井先生、副査の井田先生、細田先生には本当に感謝してもしきれない思いである。
学会ホームページは以下のとおり
http://www.the-dma.org/dmef/researchsummit/